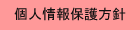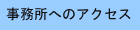- TOP
- よくあるご質問
よくあるご質問FAQ
よくあるご質問 項目
不動産登記に関して
- 1
-
権利証、登記識別情報通知、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書(納税通知書)、運転免許証、実印などです。
- 2
-
司法書士に依頼して、本人確認情報の提供を受ければ大丈夫です。
- 3
-
印紙税、登録免許税、取得税、消費税、仲介手数料、司法書士手数料、土地家屋調査士手数料、住宅ローン保証料、火災保険料、団体信用生命保険料等が考えられます。
- 4
-
相続による所有権移転登記が必要です。
- 5
-
2020年4月1日から施行です。
- 6
-
2019年7月1日から施行です。
会社法人登記に関して
- 1
-
会社には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社及び外国会社があります。有限会社については、平成18年5月1日会社法施行により、有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなりました。会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存在することとなりましたが、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用され、そのような有限会社を特例有限会社と呼びます。
- 2
-
資本金100万円の株式会社の場合、登録免許税が15万円、公証人の定款認証手数料に司法書士報酬が必要です。司法書士報酬は事案により異なりますが、5万円からです。また、設立に要する期間ですが通常ご依頼から1週間程度で会社設立の登記申請に至るのが一般的ですが、設立される会社内容等によりさらに期間が必要な場合があります。
なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7かかり、その額が15万円に満たない場合は15万円となります。例えば、資本金が3000万円の場合は登録免許税は21万円となります。公証人の手数料も資本金の額で1.5万円、3万円、4万円、5万円と変わります。
- 3
-
会社設立日(設立登記申請日)に会社は設立したことになりますが、法人名義の銀行口座開設には定款・全部事項証明書(会社謄本)・印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。全部事項証明書(会社謄本)・印鑑証明書の取得は、設立登記完了後にしか取得できないため、設立後の口座開設等の期間も加味した上でのスケジュール調整をお勧めします。
- 4
-
会社法の規定により取締役に変更が生じた時から2週間以内に登記申請する必要があります。
- 5
-
変更手続きをすることは可能です。ただし、会社法上変更を生じた時から2週間以内に登記申請しない場合には過料を課されることがあります。
- 6
-
同一人物を選任した場合でも登記は必要です。
- 7
-
会社の設立年月日以外の登記事項の変更登記ができます。ただし、資本金の額の減額は債権者保護手続き等が必要であり、官報の予約等を含めますと約2か月要します。
- 8
-
法人には、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人、中小企業等協同組合、農業協同組合、宗教法人等があります。
- 9
-
一般社団法人、一般財団法人の制度は、会社とは違い、剰余金の分配を目的としない社団または財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記によって簡便に法人格を取得することができる法人です。
- 10
-
毎年資産総額の変更登記が必要です。また、2年に1度理事長の変更登記が必要です。理事長が再任の場合でも理事長の再任の登記手続きが必要です。
相続・贈与・信託・遺言・後見・財産管理に関して
相続
- 1
-
原則、妻A(1/2)と子bcd(各1/6)全員が相続人となります。
- 2
-
原則、子bcd(各1/3)全員が相続人となります。
- 3
-
原則、実母g(1/1)が相続人となります。
- 4
-
原則、妻A(3/4)と兄弟ef(各1/8)が相続人となります。
- 5
-
実際の相続人と相続分は、相続放棄、相続人の欠格事由、推定相続人の廃除、代襲相続人、遺言、遺産分割、特別受益、半血全血兄弟、特別寄与者(民法1050条特別寄与料2019年7月1日施行)等の有無と事情で変わります。
- 6
-
原則、相続人はbcdですが、bが甲より先に死亡したため(代襲相続)、bに代わってbの子yzが相続します。bの妻xは相続しません。一方、甲死亡後にbが死亡したときは(数次相続)、bが相続した甲の遺産は妻xと子yzが相続します。
- 7
-
相続放棄をすれば、相続人でなくなるので相続しません。相続放棄は、原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出る必要があります。
遺産分割協議によって遺産を相続しないこともできますが、借金全額を遺産とともに他の相続人が引き受けたとしても成立した協議に対する債権者の同意がない限り借金は法定相続分に応じて分割承継します。
- 8
-
相続放棄は、相続が発生してから家庭裁判所に対して行う手続きですので、被相続人の生前にはすることはできません。相続開始前に他の相続人へ渡した文書によっては、相続放棄の効力は発生しません。なお、遺留分の放棄については、相続開始前であっても家庭裁判所の許可があればできます。
- 9
-
「相続放棄」の申述をすれば、遺産と債務を引き継がなくて済みます。しかし、「限定承認」により、相続債務について責任を負担する範囲を、相続した財産の範囲に限定することができます。原則、いずれも相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述することが必要です。ただし、限定承認の申述は、相続人全員で行うことが必要です。
- 10
-
甲が契約をし、保険料を支払った生命保険であっても、死亡保険金は受取人の固有の財産になり、甲の遺産には含まれないのが原則です。また、民法上と税法上でも取り扱いに違いがあります。
- 11
-
死亡退職金は、死者の収入に依存してきた遺族の生活保障を目的としているため、社内規定で定められた受取人が受取ることができる受取人固有の権利であり、民法上の遺産ではないとされています。ただし、会社の支給規定等の事情を踏まえて慎重に判断する必要があります。
- 12
-
建物の賃借権も甲の遺産としてbcdが相続します。事業に対して寄与した者がいれば、それを考慮して遺産分割協議をすれば事業の継続を図れます。
- 13
-
「相続人の中」で、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者には「寄与分」が認められます。b夫婦は、7年にわたって寝たきりの甲の介護をしてきたのですから特別の貢献といえますが、寄与分は「相続人」にしか認められません。「bの妻」の貢献はbの貢献と評価するほかありません。
しかしながら、2019年7月1日に「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続放棄者、相続廃除者、相続欠格者を除く。以下『特別寄与者』という)は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下『特別寄与料』という)の支払いを請求することができる。」と定められた民法第1050条特別寄与料が施行されますので、「bの妻」の貢献が特別寄与料として評価されることになります。
ただし、遺産分割協議が不調不可のときの協議に代わる処分の請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所への申立てができなくなりますので注意が必要です。
- 14
-
相続人のうち、配偶者、子、直系尊属に認められた(相続人であっても兄弟姉妹には認められません)被相続人も自由にできない相続人としての相続分です。
- 15
-
本来の法定相続分の1/2です。ただし、直系尊属のみが相続人のときは1/3です。甲の相続人が妻Aと子bcである場合に、甲が内縁の妻Mに全財産を遺贈する遺言をしたときでも、遺産のうち、妻Aは1/4、子bcは1/8を遺留分として確保できます。
遺留分は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与した財産(相続開始前1年間または当事者双方が損害を加えることを知っていたもの)の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定します。
*民法1044条2項3項新設2019年7月1日施行
相続人については、上記Aの相続開始前1年間が10年間に、贈与した財産の価額が婚姻・養子縁組のため・生計の資本として受けた贈与の価額に限るとされます。
- 16
-
遺留分を有する相続人は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈を知った時から1年以内または相続開始から10年以内のいずれか早い時までに、遺贈や生前贈与をもらった人に対して遺留分減殺請求することによって、遺留分相当の遺産を共有取得できます。
*民法1046条新設2019年7月1日施行により、遺留分請求権から生ずる権利を金銭債権化することになります。
「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定をうけた相続人を含む。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。」
- 17
-
総相続財産の評価と法的な整序をし、法定相続分に基づく各相続人が取得できる財産額を明確にしたうえで、再度、話し合い遺産分割協議を整えることをお勧めします。次善の策としては、遺産分割の調停の家庭裁判所への申立てがあります。遺産分割の調停がまとまらないときは、話し合いによる調停を打ち切り、審判手続きに移行して、裁判所が遺産分割の内容を決定します。調停は話し合いですが、審判は裁判のようなイメージです。
- 18
-
2019年7月1日に施行されます。
民法906条の2
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 19
-
2019年7月1日に施行されます。
民法909条の2(・・・当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。)が新設され、相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)× 1/3 × 当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額(ただし150万円が限度額)となります。
- 20
-
配偶者居住権
配偶者居住権の規律は、2020年4月1日から施行になります。
*「被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときはその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得する。ただし、被相続人が相続開始のときに居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りではない。
1.遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
2.配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき配偶者居住権の存続期間
第1030条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
配偶者居住権の登記等
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
二 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。配偶者短期居住権
第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始のときにおいて居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始のときから6か月を経過する日のいずれか遅い日二 前号に掲げる場合以外の場合
第3項の申入れの日から6か月を経過する日
2 前項本文においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
贈与
- 1
-
原則、bが生前贈与を受けた財産は、生前贈与した時期に関係なく、bが相続する財産から差し引かれます。
- 2
-
みなし相続財産(相続開始時財産1600万円 + 婚姻・養子縁組のため、若しくは生計の資本としての贈与の額200万円)× 特別受益者の法定相続分1/6 -(遺贈・贈与の額200万円)= 特別受益者の相続分100万円 です。
被相続人が持戻し(みなし相続財産に遺贈・贈与の額を含めて各共同相続人の相続額を計算し特別受益者の相続する金額から持戻し金額を差し引いて取り分とすること)する必要なしと意思表示(明示・黙示)した場合、遺留分の規定に違反しない範囲で効力を有します。ただし、2019年7月1日からは、明文をもって遺留分の規定に違反しても有効になり、遺留分権の行使をして金銭債権を取得する余地が残るだけとなります。
*民法903条4項新設2019年7月1日施行
婚姻期間20年の夫婦につき、居住用財産の遺贈または贈与があった場合、被相続人の持戻し免除の意思の推定が働くようになり、原則(推定を否定する遺言等がある場合等は別)、特別受益として相続財産に含めなくてよくなります。
- 3
-
甲とcが、負担付死因贈与契約を締結することなどが考えられます。
信託
- 1
-
「信託」とは「信じて託す」と書くとおり、ある人(委託者)が契約や遺言等の信託行為によって、信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地等の財産を移転し、受託者は委託者の設定した目的に従って、受益者のためにその財産を管理・処分等する制度です。遺言では本人死亡後の相続財産の承継しか決められませんが、信託では、その承継者の次の承継先まで決めることができます。
- 2
-
次のような場面で利用できます。
- ① 年少者の財産や高齢の親の財産を代わって親や子供等が管理したい場合
- ② 自分が亡くなった後に発生する自分の相続人の相続まで指定したい場合(30年先まで)
- ③ 子供に贈与したことを伝えず贈与し、贈与後に、贈与者が引き続き贈与財産を管理したい場合
- ④ 無議決権株式の発行に代えて株式にかかる権利を株式の議決権を有する者(受託者)と受益者とに分ける場合
- ⑤ 名義預金、名義株とみなされないための税務上の対策をとりたい場合
遺言
- 1
-
自分一人(2人以上の人が同一の証書ですることはできません。)で自書できます(自筆証書遺言)。ただし、遺言の全文、日付および氏名の自書、押印の要件をみたされなければ無効になります。文字の訂正にも方式が定まっていますので注意が必要です。
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言が何かと安心で遺言執行にも便利です。まず自筆証書遺言を作成して当座の手当てをし、後日、公正証書遺言を作成してより明確な意思を伝えることもひとつの方法です。自筆証書遺言作成サポート、公正証書遺言作成サポート、証人と遺言執行者への就任も承っております。
*民法968条2項の新設2019年1月13日施行により本文以外の財産目録(パソコン作成目録・通帳コピー・不動産登記事項証明書等)は自書することを要しなくなります。自書によらない記載のある毎葉両面へ署名捺印が必要です。自書しない目録の訂正にも本文同様訂正場所の指示・変更した旨の付記と署名・変更場所への捺印が効力要件です。
- 2
-
遺言はいつでも遺言者の意思で自由に変更・撤回できます。方法はいくつかあります。遺言書を故意に破棄して(公正証書遺言を除く)遺言の撤回をしたり、最も新しい遺言書が有効なものになる点を利用して、変更・撤回する方法もあります。
- 3
-
遺言の意味、内容の理解できる意思能力があれば可能です。
成年後見を受けている人(父)が遺言をするときは、医師2名以上の立会いと遺言者の遺言時に事理弁識能力が回復していた(欠如状態になかった)旨の遺言書への付記と署名捺印が必要です。
- 4
-
甲が、dに負担付で住宅を相続させる旨の遺言をすることもひとつの方法です。
- 5
-
2019年7月1日からです。下記が遺言執行者に関する改正民法の抜粋です。
-
(遺言執行者の任務の開始)
- 第1007条(略)
- 2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
⇒遺言執行者は各相続人に対して、遺言の内容の通知義務が課されました。
-
(遺言執行者の権利義務)
- 第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
- 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
- 3 (略)
-
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
- 第1013条(略)
- 2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
- 3 前2項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
-
(特定財産に関する遺言の執行)
- 第1014条(略)
- 2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
- 3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
- 4 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
-
(遺言執行者の行為の効果)
- 第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
⇒遺言執行者の権限が明確化されました。
- 第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
-
(遺言執行者の復任権)
- 第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- 2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
⇒遺言執行者の復任権が遺言執行者の責任において認められました。
-
(遺言執行者の任務の開始)
後見
- 1
-
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理をしたり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
- 2
-
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度(Q8参照)の二つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」、「保佐」及び「補助」の三つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
- 3
-
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
- 4
-
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象になりません。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。
- 5
-
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象になりません。
- 6
-
成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
なお、家庭裁判所が成年後見人等を選任することとなるので、申立人が希望した成年後見人等が必ずしも選任されるわけではありません。
- 7
-
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
- 8
-
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
- 9
-
審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。
- 10
-
家庭裁判所の許可がないと取下げできません。あくまでも成年後見制度は本人の保護・支援を目的としたものであるため、申立人の希望する成年後見人等が選任されなかったことを理由に成年後見制度の申立ての取り下げをしたとしても、家庭裁判所は取下げの許可を出すことはないと思います。また、成年後見人等に選任された人物が不当であるとする異議申立てをすることも認められていません。
- 11
-
できません。成年後見制度が開始すると本人が能力を回復するかお亡くなりになるまで続く制度です。
財産管理
- 1
-
司法書士法施行規則31条には、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務」が司法書士の業務の一部であると規定されています。
例えば、金融機関等において、口座名義人(またはその法定代理人や相続人全員)からの委任状・委任契約書を提示することにより、司法書士が各種銀行手続を代理することをいいます。契約内容により行う業務は異なります。
- 2
-
財産管理業務は非常に幅広いものですが、一例としては以下のものがあります。
- 1.当事者の依頼に基づく財産管理業務
- ① 任意相続財産管理業務(被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い各相続人に配分する業務)
- ・銀行預金、出資金等の解約手続
- ・株式、投資信託等の名義変更手続
- ・生命保険金・給付金請求
- ・不動産の売却
- ② アパート経営等、収益物件の管理・運営に関する業務(賃料の収受、維持管理のための工事手配、費用支出)
- ③ 不動産の任意売却業務
- ④ 相続における「限定承認」の相続財産管理人支援業務
- ⑤ マンション管理者
- ① 任意相続財産管理業務(被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議に従い各相続人に配分する業務)
- 2.法令上の地位に基づく財産管理業務
- ① 遺言執行業務(民法第1010条)
- ② 成年後見人・保佐人・補助人(民法第8条、第12条、第16条)
- ③ 不在者の財産管理業務(民法第25条)
- ④ 相続人不存在による相続財産管理業務(民法第952条)
- ⑤ 相続人が数人ある場合の限定承認(民法第936条)
- ⑥ 相続放棄(民法第940条第2項)
- ⑦ (法定の)相続財産管理業務(民法第918条第3項)
- ⑧ 財産管理者(家事審判手続法)
- ⑨ 任意後見業務
- ⑩ 破産法、会社更生法等の管財・管理・監督業務等
- 3.他人の事業の経営・・・又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
- ① 中小企業支援、事業承継等サポート等
- ② 会社や団体の役員への就任
- ③ 解散会社の清算人の就任
- ④ 企業との継続的法務顧問契約
- ⑤ 決済代理業務
- 1.当事者の依頼に基づく財産管理業務
- 3
-
訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務等は受任できません。また、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。
動産・債権譲渡登記に関して
- 1
-
動産譲渡登記については、東京法務局民事行政部動産登録課、債権譲渡登記については、東京法務局民事行政部債権登録課が管轄となります。それ以外では登記をすることができません。
- 2
-
譲渡人は法人である必要がありますが、譲受人は個人でもなることができます。
- 3
-
動産譲渡登記は、その登記をすることにより当該動産譲渡登記に係る動産の譲渡につき、第三者対抗要件を具備することができます。また、動産の譲渡については、動産譲渡登記以外にも第三者対抗要件を具備する方法がある(民法第178条の引渡等)ことから、動産譲渡登記における譲受人に優先する者が他に存在していたり、動産譲渡登記における譲受人が実体的には対抗要件を具備する第三者ではなくなっていることもあり得ます。
債権譲渡登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付通知があったものとみなされています。確定日付通知と登記通知との優劣は、確定日付通知が債務者に到達した日時と債権譲渡の登記がされた日時との先後で決まります。
- 4
-
譲渡登記に関する証明書を取得することで確認できます。証明書には、「登記事項証明書」、「登記事項概要証明書」及び「概要記録事項証明書」の3種類があります。登記事項証明書及び登記事項概要証明書はA1の法務局に請求することにより取得することが可能です。概要記録事項証明書は全国どこの法務局でも取得することが可能です。登記事項証明書の請求権者は、譲渡登記の当事者、利害関係人、譲渡人の使用人、譲渡等債権の債務者です。登記事項概要証明書及び概要記録事項証明書は誰でも請求することが可能です。
- 5
-
自動車・船舶・航空機・建設機械等他の法律で登録又は登記がされたものの譲渡については、動産譲渡登記をすることができません。未登録の自動車は登記することができます。また、タンクの中の気体又は液体の状態で保管されているガス、家畜(牛、豚、鶏等)はいずれも動産譲渡登記の対象とすることができます。太陽光発電システム等を動産譲渡登記の対象とすることも可能です。
- 6
-
特定の債務者に対して同一の債権発生原因に基づき継続的に発生する複数の既発生債権及び将来債権については、その発生期間の「始期」と「終期」を特定することにより1つの集合債権として特定することが可能です。
民事裁判・家事申立・債務整理に関して
- 1
-
司法書士は訴額が140万円以内で簡易裁判所で行われる裁判については、弁護士と同じように、原告(訴えた人)あるいは被告(訴えられた人)の代理人として裁判を行うことができます。
- 2
-
訴額が140万円を超えれば、裁判所の管轄が地方裁判所になるので、司法書士は弁護士と同じように代理人となることはできませんが、ご本人が裁判所に出向いていただくことができれば、裁判所に提出する訴状・準備書面作成等の裁判のサポートをすることは可能です。
- 3
-
訴額が60万円以下の金銭債権であれば、少額訴訟という制度があり、原則、1回で裁判は終わります。
- 4
-
司法書士が代理人として簡易裁判所で裁判を行った場合は、控訴状を代理人として提出することは可能です。しかしながら、控訴裁判所は地方裁判所以上となりますので、代理人として裁判を行うことはできません。A2参照。
- 5
-
未成年者の特別代理人の選任申立、成年後見等の申立、相続放棄、限定承認、遺産分割調停・審判などがあります。
- 6
-
プラスの財産(預貯金・現金・株式・不動産等)については、同じことになりますが、マイナスの財産(負債等)については、債権者は遺産分割協議において一人のみがプラスの財産を相続することになったとしても、相続人全員、すなわち、遺産分割協議で一切もらわない相続人に対しても請求することができ、最低でも相続分に応じて支払う必要があります。一方、家庭裁判所で行う相続放棄については、プラスの財産も相続しないですし、マイナスの財産についても相続しないということができ、債権者から請求がきたとしても家庭裁判所で相続放棄を行えば、支払いを拒否することができます。
- 7
-
原則、被相続人が亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。ただし、被相続人が亡くなってから3か月以上経った後、被相続人の多額の借金が発見されたり、被相続人が第三者の保証人となっていた等、債権者から請求を受けた場合など、被相続人が亡くなってから3か月以上経っていたとしても相続放棄が認められる場合もあります。
- 8
-
借入金を減らしたりする方法としては、①任意整理②個人債務者の民事再生③破産が考えられます。
- 9
-
任意整理とは、裁判所がかかわらない手続きで、借入金を利息制限法の上限金利で引き直し計算することによって、元本を減額し、原則として元本のみを分割支払い等で支払うという内容の債権者と和解することです。以後、和解内容に従い支払っていくことになります。なお、当初から利息制限法以内での貸し付けの場合は、元本が減額されません。それでも、利息カット等はできるかもしれません。
また、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行った結果、過払金が発生している場合には、債権者に対し、過払金の返還請求を行うことが可能となります。
- 10
-
民事再生法に基づく裁判所がかかわる手続きで、①将来において継続的に収入を得る見込みあり、無担保債務の総額が5000万円以下の人や②その中でも、サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握することが可能な人が申立てをすることができます。この手続きにおいて、再生計画が裁判所に認められ、その計画に従い返済すると、残りの債務の免除を受けることができます。
- 11
-
裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が破産者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。なお,財産が極めて少ない場合には,破産管財人を選任しないまま破産手続を終了することもあります。
破産手続開始の決定時点の債務は,破産手続の開始が決定されても,当然に返済を免れるのではなく,そのためには別に免責許可の申立てを行い,免責の許可を受ける必要があります。なお,破産をすることになった事情に浪費や詐欺行為などがある場合には免責の許可が受けられないこともあります。
- 12
-
破産開始決定がされ、免責許可決定の確定(復権)を受けるまでは資格が制限される職種もあります。警備員、生命保険の外交員、建設業、宅地建物取引士、弁護士、司法書士などです。
- 13
-
破産法第253条第1項但書各号において定められています。
- ・税金や国民健康保険料などの租税等の請求権
- ・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・暴行をして傷害を与えた被害者に対する損害賠償金など破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- ・生活費など夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権
- ・婚姻費用など夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権
- ・養育費など子の監護義務に基づく請求権
- ・生活費など親族間の扶養義務に基づく請求権
- ・個人事業主の従業員の給料など雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- ・意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権など破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- ・罰金等の請求権
コンサルティングサービスに関して
- 1
-
業務歴37年間の司法書士業に加え不動産業、太陽光発電事業の経営経験と実績に基づく各方面のコンサルティングを行います。各金融機関(銀行・ノンバンク・生命保険会社・損害保険会社等)、各役所(法務省・法務局・市役所・府庁・農業委員会・裁判所・財務局・税務署・国土交通省・経済産業省等)、各企業(上場会社・中小会社・個人事業者等)、各種団体(大阪司法書士会・一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会・一般社団法人日本財産管理協会・一般社団法人大阪公共嘱託登記司法書士協会・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート・一般財団法人関西電気保安協会・マンション管理組合等)、各専門家等(司法書士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・税理士・公証人・登記官・裁判官・弁護士・医師・看護師・介護士・ケアマネジャー・弁理士・不動産鑑定士・行政書士・社会保険労務士・建築士・地主・借地人等)との協働や関わりにより培った知見と経験に基づくサービスです。
不動産業務に関して
- 1
-
次に掲げる要点を参考にしてください。
- 1.不動産の処分にあたって明確にすべきこと
- A.不動産処分の理由
- B.不動産処分にかかる諸費用の概算
- C.希望売却価格
- 2.不動産処分時の注意事項
- A.引越し費用・解体費用・動産撤去費用・土壌汚染調査費用等は、見積を事前にとるとよいでしょう。
- B.共有者が多い場合は、事前に売却の意思確認・遺産の分配等の打ち合わせをしておく必要があります。
- 3.不動産の売却費用
- A.不動産仲介手数料
- B.売り渡し登記費用(売渡費用・抵当権抹消費用等)
- C.引越し費用(不動産決済時までに行う必要があります。)
- D.動産撤去費用(故障したエアコン・冷蔵庫・給湯器・照明器具・物置・古着・薬品等)
- E.不動産譲渡所得税
- F.収入印紙(売買契約書等貼付)
- G.解体・滅失登記費用
- H.土壌汚染調査費用(買主が調査依頼した場合)
- I.境界確定測量費用
- J.各種届出、税務申告等のその他費用
- 4.不動産の価格査定
- A.価格の査定は、色々な状況・社会情勢等により左右されますので多方面から決定しなければなりません。固定資産税評価額、路線価、倍率方式、公示地価、売買事例、地元不動産業者のヒヤリング等に基づき行います。売り出し価格は、売主様のご事情とご希望を踏まえ当社担当者と相談の上決定します。
- 5.不動産の売却依頼
- A.不動産業者の内容・営業信条等を考慮して決めます。営業活動の質と量と時間で成否が決まります。
- 1.不動産の処分にあたって明確にすべきこと
- 2
-
買主・売主双方の確定的な売買契約締結の意思表示を留保して取り交わす、売買の基本条件の概略について合意に達した段階での確認のための書面です。